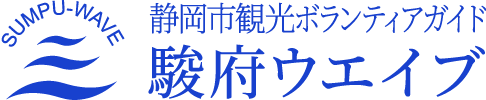「意外と知らない静岡鉄道の生い立ち・・」をテーマに3月12日(水)会員向け講演会を行いました。
「しずてつ」のルーツは、お茶の特別輸出港=清水港へお茶を運ぶための軽便鉄道にあった。
鉄道、バス、タクシー、スーパー、不動産等々毎日の生活に欠かせない地元企業・静岡鉄道の歴史と沿線開発について聴講しました。講師は静岡鉄道の出身、現在駿府ウエイブ会員である扇英樹が務め、懐かしい16mmフィルムで撮影した狐ケ崎遊園の映像も紹介しながら会員31名が静岡鉄道の生い立ちと代表的な沿線開発の話しとお茶の輸出の経緯をききました。


明治40年(1907)清水港へのお茶輸出の輸送力を増強するため、静岡・清水の有志により静岡〜清水間に軽便鉄道敷設を計画され、現在と同名の静岡鉄道株式会社(現在と同名だが、別の会社)を設立。明治41年(1908)に静岡・清水を結ぶ軽便鉄道運行開始。その後大日本軌道株式会社に買収され、大正8年(1919)には、静岡・清水の有志が更なるお茶の輸送力アップを望み、設備投資が出来なくなって衰退した大日本軌道株式会社静岡支社を買収、駿遠電気株式会社設立し、軽便から電車に変革しました。現在の静岡鉄道の前身の会社となりました。
旧静岡鉄道も駿遠電気も鉄道設立の目的は「静岡茶輸出のための清水港への輸送手段」を当時最新鋭の速くて大量輸送できる鉄軌道に求めて、いずれも地元から声が上がり、設立運動が起きている点が共通しています。
講演の後壇は、沿線開発として「狐ケ崎遊園」「静岡野球場(現草薙野球場)」にまつわるお話しがありました。
-
- ここで TEA BREAK TIME 大正9年(1920)静岡ー清水間の全線電化が完了し、電車の運行開始。これにより清水港から茶輸出は年を追って急伸。明治41年には神戸港を、明治42年には横浜港を抜いて、清水港が日本一の座に上り詰め、大正6年には全国茶輸出高の77%を占る、名実共に日本一の「お茶の港」となりました。大正14年(1925) お茶の集散地安西・茶町から清水港まで大量輸送を図るため、静岡市内線鷹匠町 – 中町間開業。その後、安西・呉服町、呉服町・中町と昭和4年まで延長するも、トラック輸送の時代となり実際には静岡市内線はお茶の輸送には使われなかったそうです。
-
- 昭和2年(1927)狐ケ崎遊園開園。開園記念として北原白秋作詞・町田嘉章作曲の新民謡「ちやっきりぶし」制作。 昭和4年(1929)自動車部新設。本格的に乗合バス事業に進出。1930年には大型貸切自動車に進出。昭和9年(1934)静岡清水線の複線化完了。 昭和20年(1945)6月空襲により、電車、バス、本社社屋などの施設の大部分を焼失。後80年となりますが、静岡鉄道はそののち80年間鉄道、バス事業から観光事業、自販事業、小売事業、不動産事業等へ市民のための事業を進めてきています。
令和4年の静岡県の緑茶(仕上茶)の出荷量は56,786,475キログラム、出荷額は1264億2400万円で、日本一となっています。生産量は、鹿児島県が2万7000トン、静岡県は2万5800トンと、静岡県は全国2位になりました。
来年令和8年(2026)は明治39年(1906)、神奈川丸が清水港に入港=お茶輸出開始から120年です。