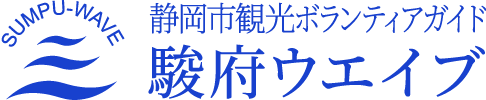しずび出前講座『浮世絵ってなんだ?』を、令和7年6月19日(木)会員向けに開催しました。
令和7年6月19日(木)会員向け研修として、しずび出前講座『浮世絵って何だ?』を、静岡市美術館の大石沙織学芸員を講師にお招きして、静岡市歴史博物館講義室にて開催しました。NHK大河ドラマ「べらぼう」で注目されている「浮世絵」の通史を中心に、流行の背景、絵師の描く浮世絵の特徴、出版のしくみなど、浮世絵を縦、横に捉えたお話を33名の聴講会員はドラマの登場人物と重ね合わせながら、興味深く聴き入っていました。最後に、大石学芸員から浮世絵の実物を見せていただき、また触れさせていただくことで、色の付け方の工夫や紙の感触を肌で感じることができました。

「浮世絵とは」
16世紀から17世紀に発達し、「近世初期風俗画」と呼ばれています。それまでは、絵として描かれる人物は位の高い人物に限られていたのが、この時期から名もなき庶民の生活が描かれるようになってきます。初期のものでよく知られているのが、狩野永徳の「洛中洛外図」です。肉筆画は富裕層からの注文を得て描かれ高価なもので、庶民には手が届かないものでした。そこで、安く手早く大量に摺ることのできる浮世絵版画が庶民の文化となっていきました。
版木の材料は主に山桜の木です。一作品にだいたい10版使われるそうですが、色版においては、版木の裏表の両面を使用し、鉋で削っては、次の彫に使い回してきました。徐々に薄くなり、彫れなくなったものは薪にしたそうです。見事なリサイクルです。したがって、江戸時代の版木が残されていないのは、火災や戦災で焼失したこともありますが、こうした理由にもあるのだそうです。
「見当をつける」
現在、日常で使われる言葉「見当をつける」は、江戸時代の「浮世絵版画」の技術から生まれた言葉です。図工の授業で多色刷り版画を作ったことのある方は経験したことがあるかもしれませんが、色を載せた版木に紙を置くときにずれはしないかと緊張しましたよね。しかし、江戸時代の浮世絵版画は10版以上もある作品であっても、全くズレることがなく完璧に色が重なっています。
なぜ、こんなにきれいに仕上がるのか。実は版木に「ヒキツケ」「カギ」という2箇所に「見当」を彫っておくのです。ここに合わせて紙を置くことでズレを防ぐ、まさに「職人技」。また、ズレがなく、ぴったりと合った美しさは、紙の質や気候によって微調整をする摺師の経験と技も生かされているとのことです。

版木の表面に彫り込まれた「見当」。左下が「ヒキツケ」。右が「カギ」。
「出版のしくみ」
版元とは、出版物の企画、制作、資金調達、絵師や職人との交渉、制作工程の管理、版木の管理、宣伝、販売など多岐にわたっての業務を担当する企画会社兼出版会社です。出版の企画を立てた版元は、絵師に製作依頼をします。絵師は依頼を受けて、墨一色で下絵を描きます。その下絵をもとに版下絵(版木を彫るための原画)を製作します。彫師は、版下絵をもとに主版(輪郭線)を彫り、校合摺(版木の墨摺)を行います。この校合摺に絵師は色さし(色を指定)をします。彫師はこの指定された色に基いて色版(色ごとの版木)を彫ります。
版元に戻った版木は次に摺師に届き、依頼通りの色で摺られます。この段階で絵師がすべての色が正しく表現されているか、途中経過を何度も確認した上で本摺に至りました。こうして一つの作品が完成すると、版元は販売に取り掛かります。寛政2年(1790年)以降は版下絵ができた段階で幕府による「行事」という検閲が入りました。浮世絵版画の画面に改印が入っているのは、このためです。
「浮世絵の黎明」
〈墨摺絵〉延宝(1673~81)
菱川師宣はそれまで本の挿絵として使われていた版画を、独立した一つの作品として世に出しました。「墨摺絵」といい、墨一色の版画に筆で色を塗る技法です。
〈丹絵〉元禄(1688~1701)
墨で摺られた版画に、主に「丹」(酸化鉛)という朱色の顔料で手採色を施したもの。これに加えて緑や黄色なども使われました。鳥居清信らが手掛けました。
〈紅絵/漆絵〉享保(1716~36)
紅絵とは、墨で摺られた版画に、植物の紅を用いて彩色を施したもの。石川豊信の「佐野川市松」が有名です。それまで石畳模様と呼ばれていた柄は、市松が付けている帯の柄から「市松模様」と呼ばれるようになりました。
漆絵は、墨に膠を入れて彩色を施したもの。艶が出て、着物の柄などに凹凸が表現され、工芸品のような技術に仕上がります。
〈紅摺絵〉寛保(1741~44)
それまでの墨摺絵に手彩色を施す「丹絵」「紅絵」等から発展したもので、版木を使って色を重ねることで、効率的に彩色できるようになりました。紅を主として緑色、黄色など、4~5色を用いるようになりました。錦絵の基礎となる「見当」の発明により、色ずれの調整ができるようになります。石川豊信は紅摺絵を代表する美人画作家です。
〈水絵〉
輪郭に墨線を使わず、紅、黄色、緑色など淡い色だけで摺られた版画で、錦絵の前に流行しました。染色用に品種改良されたつゆ草や紅花が使用されています。湿気に弱く、青色は変色してしまいます。
〈錦絵〉明和2年(1765~)
鈴木春信が「絵暦」で試みた多色摺の版画が評判となります。「太陰暦」を使っていた日本では、年によって大の月(30日の月)小の月(29日の月)が変わるので、毎年その情報を隠し絵として表現した「絵暦」が出されました。
はじめは非売品として、大名、旗本、豪商、豪農など富裕層や知識人の集まりの中でお互いに自慢し合い、交換会を行ったり配ったりしていました。『見立芦葉達磨』のように、達磨の伝説(聖なるもの)を遊女(俗っぽいもの)に置き換えて表現されたものも流行しました。この多色摺はその美しさから「錦絵」と呼ばれるようになります。春信が「絵暦」を出した1765年は「錦絵」の始まり、浮世絵のターニングポイントと考えられます。
「主要な浮世絵師」
「絵暦」により錦絵の誕生に貢献した鈴木晴信は、中世的な顔立ちの女性を描いた美人画で人気を博しました。晴信が亡くなった後、蔦屋重三郎の時代、浮世絵の黄金期となります。鳥居清長は、すらりとした八頭身の女性の描き方が特徴で、江戸のどこであるかがわかるような風景を背景に用いる手法は、のちの広重や北斎に影響を与えました。大判錦絵と呼ばれる三枚続きの作品は、一図ずつを切り離しても独立した構図が成立することも特徴の一つです。
旗本出身の絵師として有名なのが、鳥文斎永之です。狩野派を学び浮世絵師に転身します。「べらぼう」にも登場する老舗西村屋から出版されました。「紅嫌い」と言われる紅色を避けて淡い色のみで描かれているのが特徴で、知識人や上流階級から高く評価されました。この時期の江戸では、実際に着用している着物も渋めの色であったことから、渋好みが流行であったと考えられます。

約1mmの間隔に3本の髪の毛を彫っています。「毛割」(けわり)というそうです。
永之と並んで美人画で人気を博したのが蔦屋重三郎プロデュ―スの喜多川歌麿です。顔と上半身を大きく描く「大首絵」という構図を多く用い、女性の表情をはっきり表現しました。繊細に描かれた髪の毛一本一本から、彫、摺についても経験を積んだ親方級が担ったと思われます。彫については1mmの間隔に3本の髪の毛を彫るまさに「神業」。彫師の心意気が見て取れます。極細の線を彫るのは最高難度の技術で、担当できる親方クラスの彫師を「頭堀」(かしらぼり)と呼んだそうです。

喜多川歌麿「寛政三美人」(1793年)
同じく蔦屋重三郎プロデュ―スの東洲斎写楽は謎多き浮世絵師と言われています。歌麿と同様「雲母摺」の技法を取り入れ、大判錦絵でデビューしましたが、1年足らずで表舞台から消えてしまいます。大田南畝の『浮世絵類考』に「あまりに真を描かんとて あらぬさまにかきなせしかば 長く世におこなわれず一両年にして止ム」とあるように、役者の素顔をあまりに正確に描いたことが不評だったと記されています。

東洲斎写楽「市川鰕蔵の竹村定之進」(1794年)
葛飾北斎は、1830年代、西洋から輸入された新しい顔料「ベロ藍」を積極的に使用し、「神奈川沖浪裏」「山下白雨」「凱風快晴」に代表されるように従来の浮世絵にはない鮮やかな発色とグラデーションを生かした作品を描きます。ベロ藍は硫酸第一鉄とヘキサシアノ鉄Ⅲ酸化カリウム液を混ぜて作られています。原料が牛の血液ということもあり、それまで使われてきた「藍」よりも安価で求めることができたそうです。

葛飾北斎「凱風快晴」(1830~34年頃)
歌川国芳の武者絵の中でも人気のあるのが、三枚続「大物裏平家の亡霊」です。義経の一行と平家の亡霊を異なる色彩で描き、激しく波立つ海の様子を三枚に組み合わせて表現することで壮大さがひき立ちます。歌麿の時代は三枚の中の一枚でも成立するような構図になっていましたが、国芳は三枚揃えて一つの物語を成立させています。国芳は無類の猫好きでも有名で、猫をモチーフとした作品も多く残しました。
国芳と同じ年生まれの歌川広重。名所絵の名手と言われています。「東海道五十三次」は20シリーズ作られました。初版摺は「保永堂版」です。このときには、広重はまだ旅に出ていなかったと言われています。まるで行って見たかのように描いているところが、広重の上手いところでもあります。「後摺」では、描く月の大きさを変えたり、色の具合を「初版」と変えたりしています。何を中心に描くか、何を強調させるか、そこに作者の意図が見えます。「後摺」では、ついさぼり心が生まれてしまったのか、一版少なくなっていることもあるのだそうです。また、同じ場所でもたくさんのバリエーションがある「変わり摺」も残されています。同じ構図に飽きてしまったためなのか・・・実のところはわかっていません。

歌川広重「東海道五十三次・由井」(1834年)
「統制下での浮世絵」
享保の改革、寛政の改革など、幕府による統制の中で浮世絵の表現内容や出版方法にも制限が加えられ、徐々に厳しいものになっていきました。しかし、版元や浮世絵師は、その規制を逆手に取ったり、表現を工夫したりしてとことん幕府に対抗しています。寛政5年の「美人画で名前を入れてよいのは遊女のみ」という規制には、茶屋娘の名を判じ絵で表現して出版しています。歌麿は母子絵を描くことで「これは美人画ではありません。」というアピールをしていたとも言われています。
「浮世絵とジャポニズム」
19世紀フランスの銅版画家ブラックモンは、摺師の工房で有田焼の包み紙として使われていた「北斎漫画」を見つけました。これをきっかけに欧米を中心に浮世絵が人気となり、ゴッホやモネ、ロートレックにも影響を与えました。