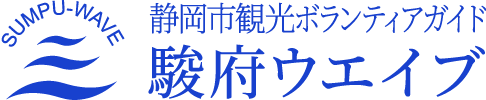丸子再発見「東海道・丸子宿を歩こう!」令和7年10月15日(水)17日(金)18日(土)開催しました。
10月15日(水)・17日(金)・18日(土)の3日間にわたって、
「東海道・丸子宿を歩こう!」を開催しました。
参加者は3日間であわせて56名。30代から80代と幅広く、
各日5名のスタッフでご案内しました。
同行した18日(日)は、晴れ間ものぞくお天気のもと、
丸子3丁目バス停から柴屋寺まで約3㎞のウォークがスタート。
なかなかの交通量がある道を、参加者は東海道の歴史や丸子宿の説明を
耳をそばだてて聞きながら歩きました。
東海道は律令時代の五畿七道の一つとして敷設されたのが始まりですが
江戸時代になって宿場が整備され伝馬制度を定めたことで、京・大阪と
江戸を結ぶメインストリートとなりました。
丸子宿は江戸日本橋から数えて20番目、宿場の中では小さいながら、
安倍川の水量が増して何日も川止めとなれば人があふれかえるなど、
重要な宿場でもありました。宿場の東西にはそれぞれ江戸方見附、
上方見附が設けられ、石垣を積み木戸を設けて立入りを監視し、
街道の見張り場でもありました。
丸子宿の中ほどにある白井酒店で、ひとやすみ。江戸時代は旅籠を営み、
酒屋となったのは明治時代からです、と言う白井酒店の奥さんのお話を
聞きながら日本酒の試飲をして、生酒のフレッシュさを味わいました。
無人販売のミカンや野菜を選びながら歩くのもウォークの楽しみ。
金木犀の香り漂うなか、問屋場跡、本陣跡、お七里役所跡をたどり、
屋号の看板を眺めて歩いていくとついに丸子宿の外れ、
茅葺屋根の店先に「とろろ汁」の提灯と暖簾が揺れる丁子屋に到着。
開店前のお店に入っていくと、資料室では大きな十返舎一九の木像が
出迎えてくれます。
ここには現在丁子屋14代目の御当主のおじいさん(12代目)が、
熱心に集めたという浮世絵「東海道五十三次」が展示されています。
ほぼすべてが初版摺り、十返舎一九の「東海道中膝栗毛」に出てくる
「名物とろろ汁」の茶店のくだりを見立て絵とした丸子の宿だけ初版が
手に入らなかったという話です。
最終ポイントの柴屋寺へは、匠宿から山に向かって進みますが、
この道は古い時代には牧ケ谷、木枯らしの森に抜けるルートとして
往来がありました。
今川氏に仕えた連歌師宗長が庵を結んだことに始まる柴屋寺は、
京都嵯峨の竹を移植し、丸子富士や近在の山々を借景にした庭園に
囲まれています。十五夜の晩に庭の東山から月が吐き出されるように
出てくる様子から吐月峰と名付けられ、毎年旧暦8月15日には月の出を、
お茶を飲みながら待って楽しむ観月会が行われています。
宗長は京都で一休宗純のもとで禅の修行をし、連歌は宗祇の弟子として
学んだことから京都での人脈を広げ、今川氏の戦国大名としての支配にも
役立ったということです。
柴屋寺ご住職の奥様による淀みのないご案内の名調子に参加者もガイドも聞き入って、そのあとも宗長ゆかりの宝物の品々を熱心に拝見していました。
柴屋寺拝観の間には、サーっと通り雨にも降られましたが、
終了後は雨上がりの道を三々五々、浮世絵の旅人さながら匠宿へ、
あるいは丁子屋へと歩いて行かれました。
参加者の皆様からは、
「散策コースとしてスポット巡りを楽しめました」、
「いつもは車で通り過ぎてしまう場所をゆっくり歩くことができて楽しかった」、
「丸子再発見」、
「柴屋寺を初めて訪れました、月見の会にも参加してみたい」、
などなどの感想をいただきました。
皆様、お疲れさまでした。