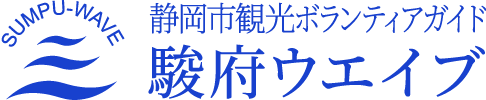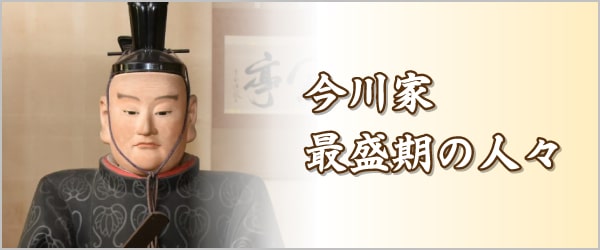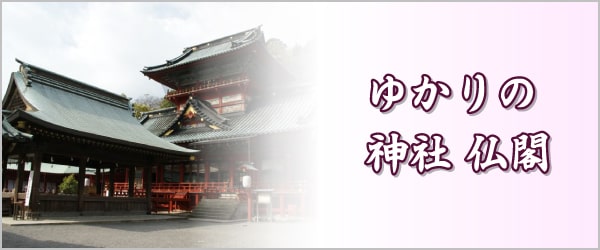今川義元公をはじめ今川家最盛期の人物と、ゆかりの寺社、山城を紹介します。
今川家は、室町・戦国時代の230年間、駿河に君臨した名家で、室町幕府の足利家の一門であり、足利尊氏が「御所(足利将軍家)が絶えなば吉良が継ぎ、吉良が絶えなば今川が継ぐ」と書き残したとされる家柄です。
暦応元年(1338)、初代範国が駿河国守護に任じられ駿河今川氏が誕生しました。公家風のイメージの強い今川氏ですが、他の大名がお手本とする領国経営を行っていました。
検地によって積極的に領内・家臣の実態把握を進めたことがあげられます。
氏親が制定した「今川仮名目録」や義元公が制定した「今川仮名目録追加」は、戦国大名が領国内に通用する法律として定めた「分国法」の代表例です。
義元公は、「桶狭間の戦いで大軍を率いながら、少数の織田信長に討たれた公家風の大名」というのは、後世に作られたイメージです。
戦乱の続いた中世の中で230年間にわたり駿府に平和の治世をもたらしました。
平和の中で武家は熱心に和歌を詠み続けました。宮廷文化への憧憬ばかりではなく、一門や家臣との結束をはかり、また合戦を前に神仏と交流し、あるいは他国との交渉にと、自らの支配を確かにするために和歌の道は不可欠でありました。
京都とのつながりも強かった今川氏には、多くの公家や文化人が身を寄せました。
義元公と家康公
家康公が75年の生涯で、3度あわせて約25年、すなわち生涯の3分の1を駿府で過ごしました。最初の駿府での暮らしは8歳から19歳まで。竹千代こと幼少の家康は、駿府で成長して元信、元康と名をあらため、義元公の親戚の築山殿と結婚し、義元公を支える武将に成長しました。この頃の家康公は今川氏の「人質」と思われがちです。しかし家康は幼少ながらすでに松平家の主として、義元公に仕えているのです。義元公も家康公を優遇し、今川氏の親族として扱いました。家康公は若年ながら駿府にあって、領地の支配を家臣たちとともに行いました。このような家康公は「人質」というより「政務見習い」としての立場であったと思われます。
家康公は8歳から19歳まで、人生の最も多感な時代の12年間を駿府で暮らし、この間、義元公の軍師でもあった臨済寺の住職・太原雪斎などから受けた種々の教えは、後に戦国大名から天下人へと成長していく過程で、家康公の人間形成の上で非常に役立ったといわれています。
- ● … 神社・仏閣
- ● … 山城